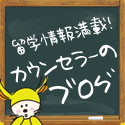2018年9月28日にオークランド大学で表彰式が行われた「JSANZ Tertiary Japanese Language Speech Contest」。後編の今回は、第3位に輝いた学生2名のスピーチ内容に加えて、ビジネス人目線で考える言語学習の重要性について語ったニュージーランド三菱商事の金属グループマネージャーを務める清水泰雅さんの寄稿文をご紹介します。
※スピーチ内容、コメントは原文のまま掲載しています。
第3位「太宰治と私 文学と私」
Vincent Nicoll-van Leeuwen(Ara Institute of Canterbury)
 2011年のカンタベリー地震が起きた時、私は高校生でした。地震の後、学校内の雰囲気がたいへん変わり、生徒も先生も、皆ずっと落ち込んでいました。私もそうでした。そして、大学に進学するか、働くか、どうするか決めなければならない時期がやってきました。その時、地震後に高校を中退した友達が現れました。
2011年のカンタベリー地震が起きた時、私は高校生でした。地震の後、学校内の雰囲気がたいへん変わり、生徒も先生も、皆ずっと落ち込んでいました。私もそうでした。そして、大学に進学するか、働くか、どうするか決めなければならない時期がやってきました。その時、地震後に高校を中退した友達が現れました。
彼は高校中退後、就職もせず、お酒に溺れ、悪事を働いたり、毎日毎日遊んでいました。私は高校最後の年という大事な時期に、その世界に引きずられていきました。それから、だんだん登校しなくなり、その友達のようになりました。そこで、久しぶりに、高校をやめずにずっと勉強を頑張っていた親友に会った時、文学が大好きな彼はリュックから本を出し、「これ読んで」とだけ言い、私に本を渡しました。
それは太宰治の人間失格という小説でした。私はそれまで文学にあまり興味がありませんでしたが、彼がいいと言うなら、読んでみようと思いました。この小説は、主人公の男が青森県から上京し、悪友にお酒、タバコ、売春婦、左翼思想を紹介され、人生を苦しみ、薬物中毒になったすえに精神科病院に入院する話です。
最初から最後まで私はこの小説に魅了させられました。「まるで私のために書かれているみたいだ」と思いました。なぜそう思ったかと言うと、主人公の他人に対しての考え方や、学校や家族などを気にせず、悪友と夜遊びばかりするといったところに自分が重なって見えたからです。
ところが、その時、まだ知らないことがありました。それは、この小説は単なる作り話ではないということです。私は何も知らず初めて読んだ時、これは太宰治がただ人間をよく分析し、リアルな主人公や世界を上手に作り上げた作品だと思っただけでした。しかし、実は、太宰治は自分の人生に基づいてこの小説を書いていたのです。ただ、彼の人生とは大きく異なる部分が1つあります。
物語の中では川に飛び込み、死のうと思った主人公は結局死ねません。しかし、実在した太宰治は人間失格を書き終わったわずか1ヶ月後に、愛人と川に飛び込み、自殺をしてしまうのです。私はこれを知った時、恐怖を感じました。この小説が彼の自伝だというなら、私も将来彼のように自ら死を選んでしまうのではないかと思ったからです。
そして、前向きで明るい人として知られていた彼でさえ、お酒や薬物によってそんな恐ろしい結末を迎えるなら、もうやめよう、他に生きる道を探そう!と思いました。つまり、太宰治の人間失格が私を目覚めさせてくれました。大事な時期に、希望がなくなっていた高校生の私を救ってくれたのです。
今もこの小説は悩んでいる若者の間でとても人気があり、私のような人を救っているでしょう。もし太宰治自身がこの小説を読んで、私と同じ気持ちを感じたとしたら、最後にあのような恐ろしい手段で自分の命を絶たなかったのではないかと思わずにはいられません。最後に、彼の名言で今日のスピーチを終わりにしたいと思います。
一日一日を、たっぷりと生きて行くより他は無い。明日のことを思いわずらうな。明日は明日みずから思い煩わん。きょう一日を、よろこび、努め、人には優しくして暮したい。
ご静聴ありがとうございます。
受賞コメント:
JSANZのコンテストで3位を取ることができて嬉しいです。いつも応援して下さるAra工科大学の先生へ心から感謝しております。スピーチを作成するのにとても時間がかかり、発表した時、たいへん緊張していましたが、参加して良かったと思います。正直に言わせて頂ければ、優勝できなかったのが本当に悔しかったですが、今後も勉強を続け、向上していきたいと思います。
第3位「日本人ハーフの二重国籍の悩み」
Vanessa Tubman(Massey University)
 みなさん こんにちは。今日は日本のについて少しお話したいと思います。
みなさん こんにちは。今日は日本のについて少しお話したいと思います。
私の名前はVanessa Tubmanです。三人兄弟で、弟が二人います。私たちは日本人の母とNZ人の父との間に生まれ、NZで生まれ育ったハーフです。弟の一人は日本人ですが、もう一人はNZ人です。なんか変ですよね。
日本人と外国人のハーフは21歳までは国籍を二つ持つことができるのですが、21歳の誕生日が来ると、国籍を一つにする必要があるのです。下の弟は21歳になり、ニュージーランド国籍を選びました。大学卒業後日本のJETというプログラムに応募して、日本の学校で英語のアシスタントとして仕事をすることを決めたのです。実はこのプログラムは日本人はすることはできないため、彼には選択のはありませんでした。
上の弟は、国籍に関してとても悩んでいて、なかなか選ぶことができませんでした。結局彼も仕事の都合で日本国籍を選択することにしたのです。二人とも仕事の都合でおい違う国籍を選ぶことになったのですが、「できれば両方の国籍を持っていたかった」と、一つの国籍を選ばなければいけないことにとても悩んでいました。
実は、私も同じ気持ちで、のとても苦労をしました。私達ハーフにとって、国籍を一つだけ選ぶというのは簡単な事ではありません。父の国、そして母の国:どちらかを選び、もう片方を捨てるという事はできないのです。
母方の親戚はみな日本に住んでいます。NZのはもういなくなり、母方のはだんだん年を取ってきていて、とても心配です。日本にいる祖母は私にとってはたった一人の「おばあちゃん」なのです。そして、祖母にとっても孫は私達3人だけなのです。そしてNZには私達の父がいます。
私達にとってとても大事な家族は両方の国にいます。これからの長い人生でもしかしたら日本に住むことになったり、NZに戻ってくる必要もあるかもしれません。私はどちらの国も大事なだと思っています。それなのに、「どちらかの国をえらべ」とせめられるのは、とてもつらい事です。今回日本人として生きていくと決心した弟はNZ生まれのNZ育ちで、を終えるまでここに住んでいたにもかかわらず、いつかNZに戻ってきたくてもその時は外国人として戻ってくることになります。
しかし日本のでは、二重国籍をもつことは許されていない。二重国籍はそれだけで犯罪なのでしょうか。私達のように日本人のハーフである、二つの国籍を持つことはどうして許されないのでしょうか。日本の二重国籍について少し調べてみましたが、いろいろな意見が書いてありました。
中には、スパイとかテロのを書いているものもあり、かなりショックでした。国の安全はもちろんとても大事ですが、国籍を二つ以上もつこと=犯罪だとは思いません。今はの時代です。これから、世界はどんどんグローバル化していく中、国際結婚も増えると思います。ハーフとして生まれてくる子供たちも増えますよね。
将来、日本の法律が変わって、私達のようなハーフがデメリットではなく、メリットのある存在としてもめて受け入れてもらえる日が来るのをっています。
私はニュージーランド人であり、それと同時に日本人です。
ありがとうございました。
受賞コメント:
3位入賞する事ができて嬉しいです。会話とは違い、スピーチを書くのはいろいろ大変でした。また、人前でのスピーチは初めてだったので緊張しましたが、とてもいい経験になりました。これからも日本語が上達するように努力を続け、将来はニュージーランドと日本のかけ橋になれるような仕事ができたらいいと思っています。
ビジネス人目線で語られる 言語習得の重要性
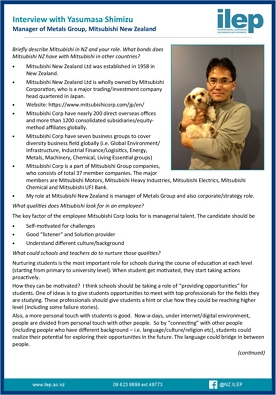 国際化が進む世の中で、徐々に減少傾向にあるという言語学習者の数。
国際化が進む世の中で、徐々に減少傾向にあるという言語学習者の数。
文化や政治、経済とあらゆる方面において、国と国とのつながりがより深まりつつある今、ニュージーランド三菱商事で金属グループマネージャーを務める清水泰雅さんは、言語学習の重要性について考えます。
言語学習を推進する非営利団体「iLep」が発行する季刊誌に掲載された、清水さんのインタビュー記事をご紹介します。(画像をクリック/タップすると、リンク先 が開きます。)
Q. 学生のうちから多言語能力を身に付けることによって、どういった影響があるのでしょう?
言語はコミュニケーションのツールでしかありません。だから重要なところはどのように使うかであって、どれだけ流ちょうに話せるかではないんです。周りの人たちと関わり、心でつながることを可能にしてくれるのが言語というツール。相手が違う文化的背景を持った人であれば、異なった視点から互いの意見や考えを交換し、より深く興味深い話をすることもできますよね。
学生のうちから多言語能力を身に付けることができれば、選択肢も広がっていく。学校卒業後にはニュージーランド国内だけでなく、海外で働くこともできるでしょう。ニュージーランド経済はそう大きいわけではありませんから、どうしても雇用のための機会が限られてきてしまいます。そこでもし他の国の言葉を話せたら、世界のどこかで自分の未来を切り開くことができるのです。
Q. ニュージーランドの求人市場において、言語はどのような役割を果たすようになると思われますか?
ニュージーランドが他国にとって有益な貿易パートナーであることは、大変重要なことです。CPTPP(包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定 ※注)に合意したことにより、ニュージーランドはより一層、世界との経済的・政治的なつながりを深めていくことでしょう。
近い将来、貿易や投資関連の仕事が増加していくことは間違いありません。そうなれば、企業側にとって多言語能力を持つ学生は必要不可欠な人材となるのです。
※注:ニュージーランド政府は2018年10月31日に、CPTPPが2018年12月30日に発効すると発表した。
Q. 他に伝えたいことはありますか?
前述の通り、言語はコミュニケーションのツールです。他の言語を学ぶということは視野が広がるというだけでなく、人としても成長させてくれる素晴らしい機会になるでしょう。
- 寄稿文掲載 News Letter:
- https://www.ilep.ac.nz/sites/ilep.ac.nz/files/Newsletters/Newsletter%202018%203%20(1).pdf
- 寄稿文提供:
- ニュージーランド三菱商事 清水泰雅金属グループマネジャー
- ニュージーランド三菱商事:
- 1958年設立。
- 交通インフラや物流、金融、資源などの分野においてビジネス展開をしている総合商社「三菱商事」の現地法人。
- 清水さんが務めるのは、金属グループのマネージャー。
- https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/network/ao/newzealand.html
- iLep(International Languages Exchanges and Pathways):
- ニュージーランドの教育機関や教師に対し、オークランド大学運営のもと、言語学習のカリキュラム実行支援を行っている。
- 日本をはじめ、中国、フランス、ドイツ、スペインなどのナショナルアドバイザーが在籍。
- https://www.ilep.ac.nz